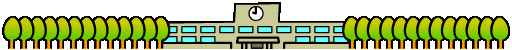
光の色

黄色光源装置
| 黄色に見える光には大きく分けて二種類あることを受講者に体験してもらうために製作した装置です。 光源Aと光源Bはともに黄色(少しオレンジっぽい)に見えますが、光の種類が異なります。一方は単色発光LED、もう一方は3原色によるフルカラーLEDを調整して黄色に発光させています。 |

| 図1 簡易分光器で見たいずれかの光源 右側の光が入ってきた光、左側の2つが分光された光で、右が緑、左が赤に見えます(安価なデジカメで撮っているのと補正が入るので色の再現性が低いですが)。そして、黄色の成分が見えていいないので、単色で黄いろに相当する波長の光は含まれていないことがわかります。 |

| 図2 簡易分光器で見たもう一方の光源 右側の光が入ってきた光、左側が分光された光で黄色に見えます。単色といってもレーザー光のように波長の分布が狭くないので、黄色の周りに少し黄色以外の光が混ざってしまっています。 なお、どちらが単色なのかを明記していないのは、受講生がこのページを見てずるしないようにするためです。 |
| ディスプレイの表面を拡大したものを見せたり、画面上でシミュレーションして見せたりしても実感を持っては理解しづらいようですが、目の前にある(ほぼ)同じに見える光が分光器を通してみると違うというのを実感すると、驚いている受講生も多数います。講義で説明した後に見せているので、「なるほど」と思って欲しいところです。講義での説明だけでは形だけ理解したつもりになっていて実際には何を意味するのかわかっていないということですね。自分の目で見ても何を言っているのかわからないという受講生もいるので困ります。情報過多の時代で、知識が知識、あるいはテストの正解はテストの中だけのことなってしまっているのでしょうか。 |
| なお、この光源装置の一方はフルカラーLEDなので、スイッチと輝度調整つまみで各色の強さを変えると様々な色が出せます。かなり細かく調整しないといずれかの色が強く見えるのと、デジカメの色補正により色が変わってしまうので再現性は高くありませんが雰囲気は伝わりますよね。 |
 赤 |
 緑 |
 青 |
 青+赤 |
 青+緑 |
 赤+緑+青 |
元のページに戻るときは、ブラウザーの戻るボタンをご使用ください